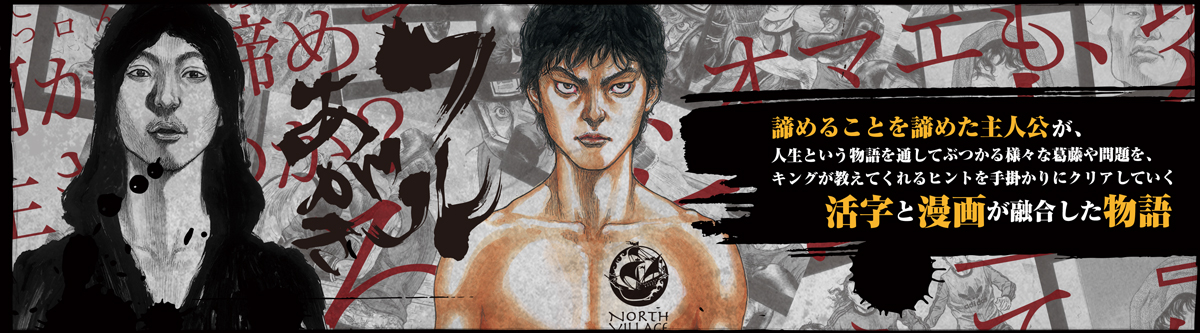
「自分は天才だ」と信じ込めば何でもできる。どんなに不利な状況でも、自分の意志を貫き、思うがままの現実を成し遂げる方法
我らが『NORTH VILLAGE』の長、北里洋平。
尊敬する人生の師たちの自伝にこだわった出版社、
世界で一番の店舗数を持つシーシャカフェ、
宝の数々が行き交う世界に魅せられて立ち上がったリサイクル事業、
これからのアジトの候補地を探求するための不動産業。
ジャンルも様々な4つの事業を取りまとめる彼の自伝『ワルあがき』では、
自己肯定感満々な幼少期から、数々のチャレンジと挫折とを経て、
その度に自身を奮い立たせながら歩んできた今日までの日々が、
赤裸々に綴られています。
キーパーソンとなるのは、主人公を叱咤激励し続ける謎の人物、「キング」。
一体、彼の正体とは…?
「そんなことある?!」と感じられてしまうほど奇想天外な、数々の実際のエピソード。
数多の経験を通じ学んでいく主人公の等身大な物語を、せひお楽しみください。
さぁ、冒険を始めよう
子どもの頃、学校で先生に何度も言われた、
「マジメに」「勉強熱心に」「いい子でいなさい」。
でも、オトナの用意した学業というレールを走り抜けると、
行き着いた先は就職活動だった。
いやいやいや、ちょっと待ってくれよ。就職だけが正解だったのか?
他に生きていく選択肢はなかったのかよ。
まだ俺、学校から大事なことなーんも教わってないぞ。就職先なんか決めるより、
まずはどんな生き方をするかを決める方が重要だったんじゃないのか?
いい点数のとり方よりも、夢の叶え方を教えてくれてたらよかったのに。フザケンナ。
もうオトナの言うこと聞くのヤーメた!
「いい加減諦めろ」「現実を見ろ」。
はあ? そんなこと、
やりたいことぜーんぶ諦めてきたようなオトナに言われたかないよーだ!
俺の人生だ。今日も、明日も、死ぬまで自由だ。
さあ、冒険を始めようか。
キングとの出会い〜我がままを、貫け〜
誤解を恐れずに言えば、俺は、裕福かつ幸せな家庭で育った、我がまま坊ちゃんだった。
そしてさらに誤解を恐れずに言えば、「天才」だった。
自分で自分をそう思うようになったきっかけは、母親から言われたこんな言葉だった。
「あなたを生んだ時に、お父さんとお母さんはあなたに十二分な才能を授けたわ。
もしあなたが今後の人生で、何かができない、誰かに勝てない、ということがあれば、
それは才能のせいではなく、あなたの努力不足ということよ」
自分の年齢を「永遠の二十歳」と言う以外、噓をつく姿を見たことがなかった母親が、サラッと言ったこの言葉を、子どもの頃のピュアな俺は、言葉通りに、特に「才能」の部分をピックアップして、鵜呑みにしていた。
それは、随分と大人になった今でもだ。
「俺は自分のことを天才だと思うことにかけて、天才なんだ」
自分を天才と思い込めるからこそ、「どんな夢でも不可能ではない」と、挑戦できるのだ。
そんな幼少時からの天才にも、悩みはあった。
「天才なのに何者にもなれていない、普通の子ども」である自分が嫌だったのだ。
そんな最中、学校の学芸会で、『裸の王様』のお芝居をやることが発表された。
小学校4年生、10歳のときだった。
先生が黒板に役名を書いていく中で、もちろん、「主役」という響きが気になった。
「でも主役に自分で立候補するとかって、
気合入りすぎちゃってるみたいで恥ずかしいな…」
そんなことを考えてモヤモヤしていたその瞬間、誰かに背中を思いっきり叩かれた。
思わず振り向くと、そこには知らない1人のおっさんが立っていた。
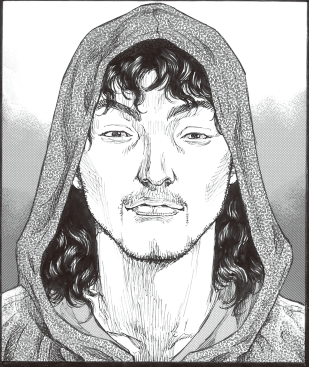
「よう」
「…おじさん、誰?」
おっさんは眉をしかめ、俺をじっと見つめている。ふと、俺の後ろにある黒板に目をやり、
ふんふん、と頷いた。
「王様。…いいね。いや、キングの方がカッチョいいな。うん。俺様、キング」
子どものような笑顔でおっさんは言った。
「で、オマエは何者なんだ? 何者になりたいんだ?」
おっさんは、俺の、天才が故の悩みをいきなり突いてきた。
戸惑う俺。それを見て、おっさんは、唐突に突然水槽の中に手を突っ込み、金魚を摑み、そのまま丸呑みした。

「ちょっと!」
俺は思わず言った。
「今のちょっと、はなんだ?
ちょっと待って、常識的に金魚って食べないでしょ、の、ちょっとか?」
言っていることはなんとなくわかるが、ついていけない。
「話にしっかりついてこい。天才だろ?」
キングはニヤリとした。
「迷ってもいい。わからなくてもいい。聞きたいことがあるんなら聞け。
言いたいことがあれば言え。でもな、常識というツマランもんにとらわれるな。
そんなもんにとらわれた発言はもうするな。いいな」
キングは数回首を振り、口の前で右手をグーにすると、軽く咳払いをした。
「オマエ、ドラクエ知ってるか?ドラクエは、職業、選べるよな?勇者、戦士、僧侶、魔法使い、遊び人。どれでもいいんだよな?…じゃあ、現実とドラクエは何が違う?」
ドラクエはゲームだから現実とは違うじゃん、と言おうとして、キングを見返した。
その瞬間、俺は雷に打たれたように全身がビリビリした。
もしかして、そういうことか!
「10年後、俺が大人になった時、学芸会じゃなくて、
現実社会での自分の役が決まるんだね!
だとすれば、俺は自分がやりたい役をやる。今も。これからも。それで、10年後、
俺が大人になっても、俺は俺のやりたい役を選べばいいってことだよね?
誰に何言われても。常識的に無理って言われても!」
キングは、しかし、真顔で俺を見て、言った。
「我がままって言うんだ、それ」
「え?」
キングは、とても丁寧に、言葉をひとつひとつ置くようにして言った。
「我がままを、貫け。その役をやると決めたら、それがオマエだ。
その役が、オマエそのものなんだ。我が、まま。あるがまま我がままに、だ。」
「…わかった。
…俺、誰よりも我がままになる! で、そのためには、我がままでいられるように頑張らなきゃいけない。我がままを貫き通せば、大人になった時、俺は、
本当になりたい自分になれてるはず。そうだろキング?」
俺は黒板を振り返った。皆、俺を見ている。
俺じゃなくてキングを見ているのか?と思って振り返ると、そこには誰もいなかった。
俺は、幻のように消えたキングに、心の中でサンキュー、と伝えると、再び先生に向き直り、右手を真っすぐに上げて宣言した。
「俺は、主役以外はやらない!」
かくして俺は、無事主役の座をいとめた。ばかりでなく、俺は5年生の学芸会でも、その後、転校した先の6年生の学芸会でも、もちろん主役となった。3年連続だ。
後に俺が、「ジュニア級主役争奪戦3連覇」と呼んだ、我がまま伝説の幕開けだった。
この本は、我がままを貫き通すべく、
どんな場所でも誰に対しても「ワルあがき」を続け、
いつか自分の夢は全部叶うと信じてやまない、天才的におバカな俺が主人公の物語だ。
チカラワザ〜オマエはオマエの誇りを守れ〜
6年生の夏休み、俺に、転機が訪れた。突然両親に告げられた、引っ越しと転校。
行き先は、南米大陸にあるチリ共和国。地球の反対側だ、という父親の説明に、
俺はドキドキしっぱなしだった。
それがなんだ?
大陸は違えど、同じ人間だ。言葉は違えど、心は伝わるはずだ。
やりたいようにやってやる。
誰に何を言われても、ワルあがきしてやる。
見知らぬ国の入り口に立って、でも俺は、
これは絶対面白い毎日になるぞ、と確信していた。
自分には南米の血が流れているんじゃないかと思うほど、
空気が肌に馴染むのを感じていた。
そして、海外という土地がそうさせるのか、
日本にいた頃には感じられなかった最高の解放感があった。
転校初日。俺が入学したのは、「ニド・デ・アギラス」という名前の、
幼稚園から高校までの一貫教育を行うインターナショナルスクール。
スペイン語で、「鷹の巣」という意味らしい。
「鷹」という響きが、単純にカッチョいい。よっしゃ!なったろうじゃねーか、鷹に!
クラスメイトは、世界各国から集められた鷹の卵たち。
ま、最初に鷹になるのは俺だけどな、と勝手に優越感に浸っていた。
学校での文化は、どれもこれもが日本とは違っていた。
体育の時間も、体育着なんてなかった。ほとんどが私服のまま。そして、服装同様、体育の授業自体もユルかった。
先生は思いついたように言った。
「じゃあ、今日は野球でもしようか」
野球ね。じゃあ、一番目立つ、ピッチャーしかないでしょ。
あの日、なりたい自分になる、と決めた俺は迷うことなく、自分自身の我がままに従った。
しかし、ピッチャーマウンドへ向かったのは、俺だけではなかった。
俺を合わせて6人のピッチャー候補(全員自選)が、マウンドに集まった。
俺はそのとき、日本の小学校で、いかにぬるま湯に浸かっていたかを痛感した。
あの場所では、俺がダントツに我がままだった。しかしこの国は、
というよりも南米のヤツらは、ナチュラルボーンの我がままなのかもしれない。
そのまま抗争になった。しかし、いくら発言しても、こんなにも近くで話しているのに、俺だけまったくコミュニケーションが取れない。勝負の土俵にすら立てない。
分厚いガラスのようだった他のヤツらとの距離感は、いつしか透明度ゼロの大きな壁となっていた。
次第に俺は、ジェスチャーをすることさえ虚しくなり、立ちすくんでしまった。
「誰よりも我がままである」という勝負に、俺は負けたのだ。
「俺の我がままは所詮、日本という小さな島国でしか通用しない程度のものだったのか…」
その日の帰り、またもキングが現れた。
「オマエさー、何あっさり負けてんの?」
「だって喋れないんだもん」
「だって、だってなんだもん、か。やっぱりガキのまんまだな。努力が足りなかったんだろ?言い訳すんな。結果が出せなかった、それだけだろ?」
キングの鋭いデコピン。でも、色んな意味で目が覚める。
「オマエ、ジャイアンは好きか? 普段の弱いものいじめするジャイアンではなく、
映画のジャイアンがイカしてる理由がわかるか?」
「…自分より強いヤツと戦うから?」
キングは頷いた。
「いいか。オマエは、ペラペラにスペイン語が喋れるようになるまで2年間も、
大人しく我慢して生きるのか?
力を使うにせよ、人を殴らない力の使い方だってある。
言葉で負けたんなら、力でねじ伏せろ!
仲間がいなかろうが守るべき人がいなかろうが、オマエはオマエの誇りを守れ!
簡単に負けを認めてんじゃねぇ!」
これまで、たしかにスキルも何もないまま、口先だけで我がままを通してきた。
でも今回は、口先、という武器が効かない。ならば、言葉が要らない勝負で挑めばいい。
万国共通、力の勝負だ。
「我慢なんてクソ喰らえ!」
翌日から、俺は戦士になった。
同学年の男たちに、男と男の力勝負、腕相撲を次々に挑んでいった。
もちろん勝負に負けることもあったが、俺は勝つまでやった。
勝つまでやれば負けじゃない、そう信じていた。
そんな触れ合い(主に力比べか殴り合いだが)によって、
コミュニケーション能力も向上した。
そして、その頃にはクラスメイトたちに、
「ヨウヘイはTOO SELFISHだよ!」
と言われるまでになっていた。
学年で一番我がままなのは、あの日本人だ。
その言葉は、俺にとっては勲章だった。




